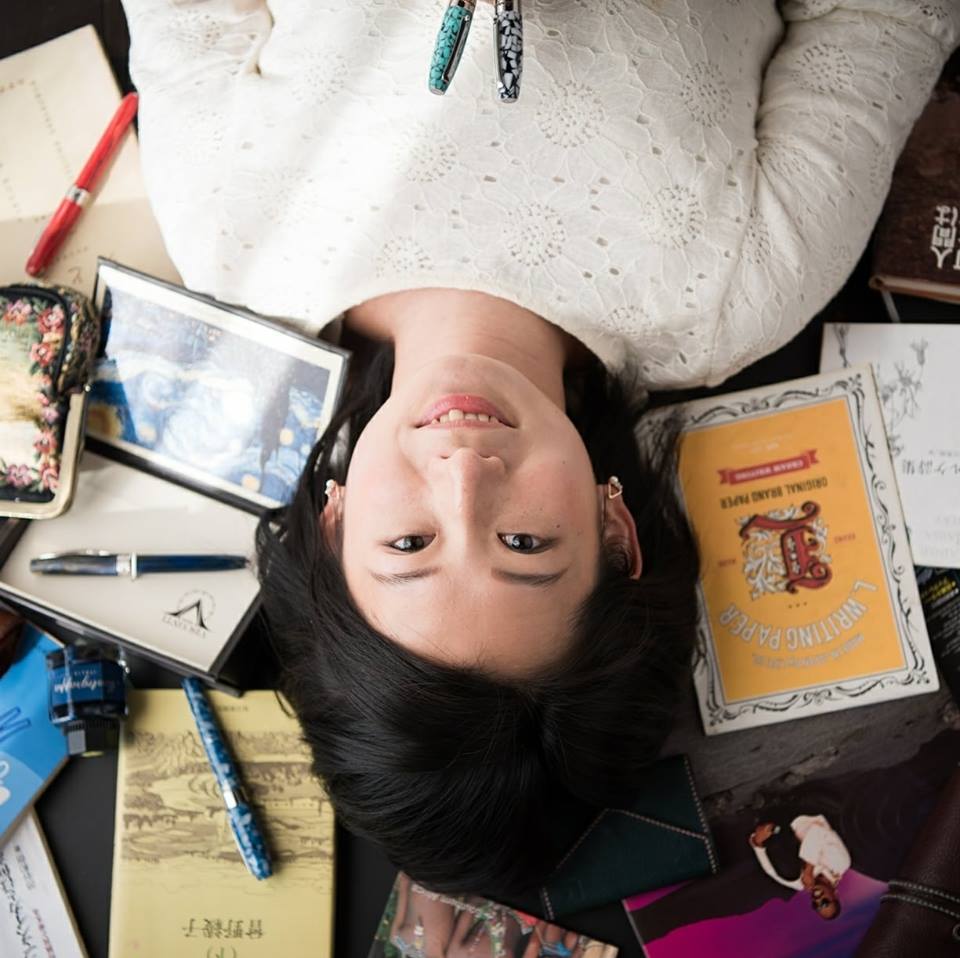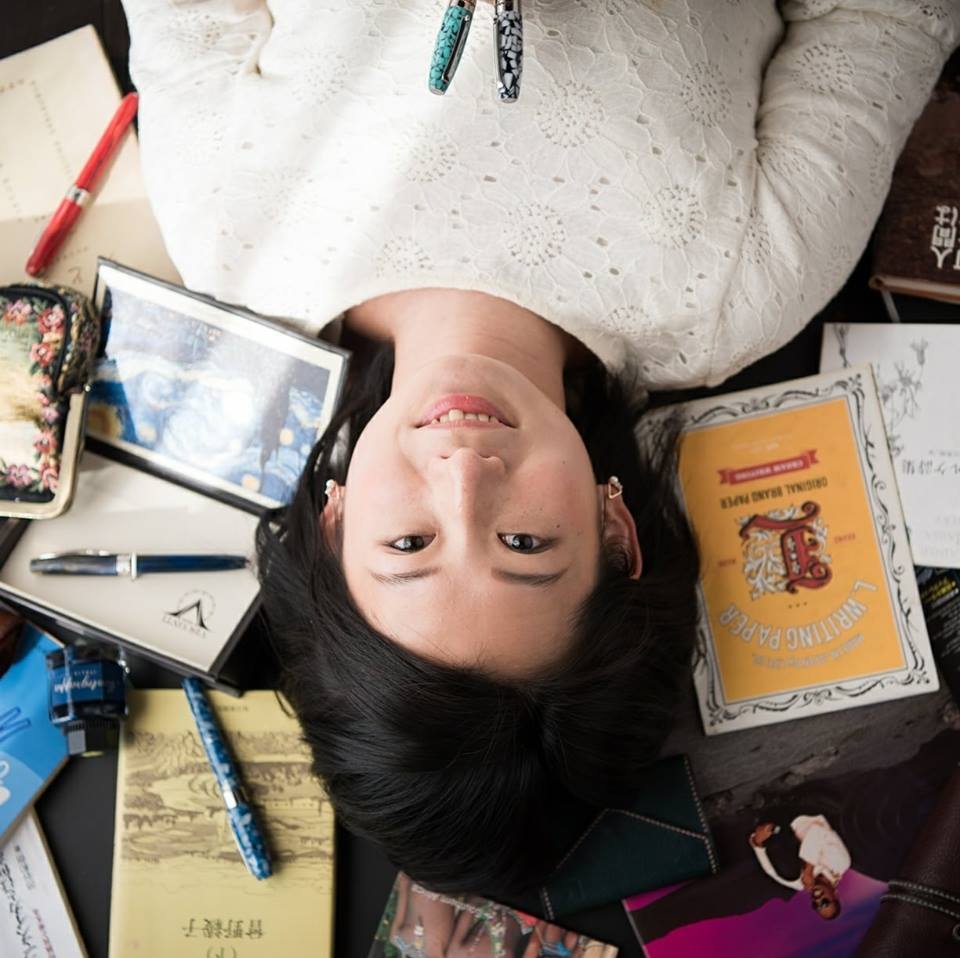もくじ
- 1 1.はじめに|このコラムについて
- 2 2.ボトルのデザインいろいろ
- 3 3.インクの種類(染料インク・顔料インク・古典インク)
- 4 4.ブルーインクの色の比較
- 5 5.インクと紙には相性がある!
- 6 6.粘度と書き味の関係
- 7 7.粘度とインクフローの関係
- 8 8.表面張力とインクフローの関係
- 9 9.気液交換とインクフローの関係 -ペン芯の構造がインクフローに影響を及ぼす-
- 10 10.万年筆の棚吊りについて
- 11 11.万年筆インクの水素イオン指数pH (酸性・中性・アルカリ性)
- 12 12.万年筆インクの濃淡
- 13 13.パイロットインクのレビュー
- 14 14.終わりに
- 15 15. 万年筆調整師より、インクについてミニコラム
- 16 16.参考文献
1.はじめに|このコラムについて
こんにちは、わたしはつくしと申します。
先日、Il Duomoでモンテグラッパのインクを購入して、レビューを書いたのですが、
モンテグラッパのユーザーだけでなく万年筆の幅広いユーザーの方にインクのことを伝えたいという想いがあり、
この記事を書くことにしました。
万年筆インクとひと口に言っても、とてもバラエティーが豊かです。
たくさんあって選ぶのが難しい、とか、どういう基準でメーカーがインクづくりをしているか気になる、という意見もあるかと思います。
こちらの記事では、万年筆インクについてもっと詳しく知りたい!
基礎知識をできるだけ専門的に知りたいというかた向けに説明しています。
もちろんボトルのデザイン、インクの色、インクの粘度などの要素は人によって感覚が異なりますが、
このコラムは私の主観も入りつつ、なるべく客観的な意見を中心にしてみました。
とはいえ、1人のユーザーの意見なので、メーカーの見解と異なる場合もあります。
様々なメーカーのインクの購入を検討する上で、参考資料として読んでいただけたら光栄です。
(長文なので目次から拾い読みしていただいても大丈夫です。)
2.ボトルのデザインいろいろ
万年筆インクは、ボトルも魅力の一つと言えましょう。ボトルのデザインはメーカーやレーベルによって様々です。
インクが少なくなっても吸入しやすいようにデザインされていたり、芸術的な意匠のボトルもあります。
素材はガラスが主ですが、まれにプラスチックも存在します。
図3 モンテグラッパのボトル

図4 ビスコンティの旧ボトル

図5 モンブランのボトル
3.インクの種類(染料インク・顔料インク・古典インク)
さて、本題のインクの種類について学んでいきましょう。
万年筆のインクには染料インク、顔料インク、古典インクの3種類があります1)。
インクブームでいろいろなインクをコレクションしている方もいらっしゃいますが、
この3種類は用途やメンテナンス方法が異なるため、どのインクがどの種類に属するのかは、きちんと把握しておく必要があります。
染料インク
- 色材に染料が使われていて、水に溶けやすい。
- 水に濡れるとにじみやすくて、光に弱く退色 (色あせ) するので、文章の長期保存には適していない。
- 用紙の繊維の中まで入り込むので、筆跡に濃淡が出やすい。
- ペン先で詰まったインクを洗い流しやすく、万年筆内部のトラブルは起きにくいので、万年筆のメンテナンスをしやすい。
- 最も一般的なインクで、色のバリエーションが豊富にある。
- モンテグラッパのインク、パイロットの色彩雫、セーラー万年筆の四季織などは染料インクである。
顔料インク
- 色材に顔料が使われていて、耐水性、耐光性に優れている。
- 染料インクと比べると、筆跡がはっきりとしていて、にじみにくくて、裏抜けしにくい。
- 用紙の表面に付着するので、筆跡に濃淡が出にくい。
- ペン先および万年筆内部で詰まったり、固まってしまうこともある。
- しばらく使わない場合やインクを入れ替える場合は、ペン先と首軸をインククリーナーキットできれいに洗浄する必要がある。
- 染料インクと比べて色のバリエーションが少ない。
- セーラー万年筆のストーリア、プラチナ万年筆の水性顔料インクなどが顔料インクである。
古典インク (没食子インク)
- 染料インクに鉄分と酸性分を加えて作られたインクである。
- 初めは染料の青色で、時間が経過すると染料は退色するが、鉄分は酸化して黒くなり用紙に定着する。
- 耐水性・耐光性に優れていて、文章の長期保存に適している。
- 染料インクの成分が含まれているので、筆跡に濃淡が出やすい。
- ペン先や万年筆の内部でインクが乾燥したり固まると、洗浄することが困難になる。
- ペン先と首軸の金属リングの腐食を防ぐために、インク吸入後はペン先と首軸をきれいに拭く必要がある。
- 染料インクと比べて色のバリエーションが少ない。
- ペリカンのブルーブラック、プラチナ万年筆のブルーブラック、クラシックインクなどが古典インクである。
このように、まったく性質が異なるインクが3種類あるのです。
古典インクは、色が変化するのもおもしろく近年人気が再燃していますが、メンテナンスには注意が必要です。
インクの使い方の注意事項、インクの吸入方法などについてはこちらの記事をお読みください。

この章のまとめ:
・万年筆インクには主に3種類のインクがあり、それぞれに注意点があるので、用法を守って使いましょう!
4.ブルーインクの色の比較
さて、インクにはいろいろな色が存在します。この色の絶妙な違いがインク集めの楽しみとも言えます。
ここではモンテグラッパ、モンブラン、ペリカンの3社のブルーインクの色を比較します。
モンテグラッパのブルー、モンブランのロイヤルブルーは乾くと濃い紺色になります (図6、7)。
この青色はイタリア人のイメージする海を形にして表したものだと私は考えています。Il Duomoのホームページに掲載されているサンプルよりも若干明るい色になります。
ペリカンのロイヤルブルーは乾くと、若干紫色が入った鮮やかな青色になります。 (図8)。
一言でブルーと言ってもメーカーごとに色彩が異なるのはインクの魅力ですね。

図6 モンテグラッパ ブルー 万年筆:モンテグラッパ 1930エキストラ(旧型) (極細EF)

図7 モンブラン ロイヤルブルー 万年筆:モンブラン マイスターシュテュック シルバー・バーリー (細字F)

図8 ペリカン ロイヤルブルー 万年筆:ペリカン スーベレーンM800 (中字M)

この章のまとめ:ブルーのインクとひとくちにいってもメーカーごとに色彩が異なる。
5.インクと紙には相性がある!
インクと万年筆の相性、ということはよく言われますが、インクと紙の取り合わせにも相性がある、
ということも実は重要な点です。(インクと万年筆の関係性については6,7,8章で説明しますね)
用紙によって線幅 (筆跡の太さ) が変化するのかモンテグラッパのブルーインクをエキストラ (EF) に入れて検証します。
ミドリのMDノート、LIFE (ライフ) のSCHOPFER (シェプフェル)、マルマンのMnemosyne (ニーモシネ)、コピー用紙の4つの紙で試筆します。
にじみとは、用紙の表面においてインクが紙の繊維に染み込んで広がること、
裏抜けとは、用紙の裏面の繊維までインクの染み込みが到達することです。
コピー用紙はにじみやすくて、4つの紙の中でコピー用紙だけインクが裏抜けします。
このことから、コピー用紙は他の用紙より吸水性が高いことがわかりました。
対して、他の3つの紙はにじみにくくて、EFらしい細い筆跡になりました。
総じてみると、モンテグラッパのブルーインクは、4つの紙の中でニーモシネが1番自分に合いました。

図9 ミドリのMDノートにモンテグラッパのブルーインクで試筆

図10 ライフのシェプフェルにモンテグラッパのブルーインクで試筆

図11 マルマンのニーモシネにモンテグラッパのブルーインクで試筆

図12 コピー用紙にモンテグラッパのブルーインクで試筆
インクフローとは
そもそもインクフローとは何でしょうか?
インクフローはペン芯からペン先へ送るインクの供給量のことで、用紙のインクを引っ張る力ではありません。
同じ万年筆・同じインクを使用したとき用紙を変えてもインクフローは変化しませんが、
用紙のインクを引っ張る力 (吸水性) によりにじみやすさ及び裏抜けの程度が変化します。
用紙の吸水性が高いとき、にじみやすくて裏抜けしやすくなり、
用紙の吸水性が低いとき、にじみにくくて裏抜けしづらくなることが示されました。

この章のまとめ:
・にじみとは、用紙の表面においてインクが用紙の繊維に染み込んで広がることである。
・裏抜けとは、用紙の裏面の繊維までインクの染み込みが到達することである。
・インクフローとは、ペン芯からペン先へ送るインクの供給量のことで、用紙のインクを引っ張る力ではない。
・用紙の吸水性が高いとき、にじみやすくて裏抜けしやすくなる。
・用紙の吸水性が低いとき、にじみにくくて裏抜けしづらくなる。
6.粘度と書き味の関係
さて、ここからは、よく言われる「インクの粘度」について書いていきます。
粘度は物質の粘り気を表しています。粘度が高いときドロドロしていて、粘度が低いときサラサラしています。
例えば、絵の具を想像するとわかりやすいですが、水をあまり含まない絵の具で絵を描いた時、
水をたっぷり加えた絵の具で絵を描いた時、筆の進み具合が違いますね (図A)。

図A 絵の具のスケッチ
それを踏まえて読んでいただければと思います。
インクの粘度の違いが書き味に及ぼす影響はどのようなものでしょうか。
『趣味の文具箱 vol.40』の「万年筆のインクの表面張力と粘度の値」を参考にして、
インクはモンテグラッパのブルー、ブラック及びペリカンのロイヤルブルー、ブラックを選びました2)。(表1)

表面張力の単位はmN/m (ミリニュートン毎メートル)、粘度の単位はmPa・s (ミリパスカル秒) です。
単位は難しいので覚えておかなくても大丈夫ですが、表面張力も粘度も、
数値が高ければ高いほど表面張力や粘度が高くなるということです。
(この雑誌内ではモンテグラッパのブラックのインクは表面張力と粘度の値を記載されていませんでした。)
表1には、今回のコラムで使用したメーカーのインク、20℃の水 (基準値) における粘度・表面張力・pH値を載せました1) 2) 3) 。
ペリカンのブラックは粘度が高く (20℃の水の約1.5倍)、ペンポイントと用紙の間に生じる摩擦が小さいため、滑らかな書き味になります(図13)。
モンテグラッパのブルー、ペリカンのロイヤルブルーの粘度は低くてペンポイントと用紙の間に生じる摩擦が大きいため、しっかりとした書き味になります(図14,15)。
ペリカンのロイヤルブルーの粘度は水に近くてサラサラでニブを洗浄しやすいので、実店舗において万年筆の試筆で頻繫に使用されます。
モンテグラッパのブラックは、ブルーと同様に粘度が低くてしっかりとした書き味です(図16)。
従って、万年筆のインクは粘度が高いとき、ペンポイントと用紙の間に生じる摩擦が小さいため、滑らかな書き味になり、
粘度が低いとき、ペンポイントと用紙の間に生じる摩擦が大きいため、しっかりとした書き味になることが示されました。

図13 インク:ペリカン ブラック 万年筆:トレドM900 (極細EF)

図14 インク:モンテグラッパ ブルー 万年筆:エキストラ地中海ブルー (極細EF)

図15 インク:ペリカン ロイヤルブルー 万年筆:スーベレーンM800 (中字M)

図16 インク:モンテグラッパ ブラック 万年筆:フェリチータ (細字F)

この章のまとめ:
・粘度は物質の粘り気を表していて、粘度が高いときドロドロしていて、粘度が低いときサラサラしている。
・粘度が高いとき、ペンポイントと用紙の間に生じる摩擦が小さいため、滑らかな書き味になる。
・粘度が低いとき、ペンポイントと用紙の間に生じる摩擦が大きいため、しっかりとした書き味になる。
7.粘度とインクフローの関係
今度は、インクの粘度の違いが乾きやすさに及ぼす影響について検証します。再び表1を見てみましょう。

ペリカンのブラックは粘度が高くて、モンテグラッパのブル-は粘度が低いです。
ペリカンのブラックとモンテグラッパのブル-の表面張力は近いですね。
この2種類のインクをモンテグラッパのフェリチータ (F) に入れてインクの乾きやすさを比較します。
このフェリチータのような両用式の万年筆は、コンバーターに色のついたインクを入れると色彩を楽しむことができます(図17)。

図17 フェリチータのコンバーターにモンテグラッパのブル-インクが入っている様子
透明な吸入式万年筆(デモンストレーターなど)もインクの色を楽しめますね。
用紙はマルマンのMnemosyne (ニーモシネ)を使用します。

図18 粘度と乾きやすさの関係 (5秒)ペリカン ブラック(上)、モンテグラッパ ブル-(下)
図18はペリカンのブラック、モンテグラッパのブル-で文字を書いて、それぞれ5秒後に指で擦った様子です。
ペリカンのブラックで書いた文字はモンテグラッパのブル-で書いた文字よりインクが広がり汚れています。
ペリカンのブラックのように粘度が高いとき乾きづらくて、モンテグラッパのブル-のように粘度が低いとき乾きやすいことが示されました。
粘度が高いインクを使用して、縦書きで文字を書く場合、左利きのユーザーが横書きで文字を書く場合は手で擦って用紙を汚さないように気をつけるべきですね。
次に粘度の違いが用紙のインクフローに及ぼす影響について検証します。
万年筆はペリカン トレドM900 (極細EF) を使用して、ペリカン ブラックとペリカン ロイヤルブルーのインクフロー、
にじみやすさ及び裏抜けを観察します (ペリカン トレドM900は図13を参照)。
ペリカン ブラックはペリカン ロイヤルブルーの約1.5倍も粘度が高くて、両者の表面張力は近いです (表1参照)。
ただし、私が所有しているトレド (極細EF) のインクフローは多くて、ペリカンの細字Fの字幅に相当します。
紙は吸水性の良いコピー用紙を使用します。筆圧、筆記角度、筆記速度、用紙により、にじみやすさ及び裏抜けの程度は変わることをご了承願います。
粘度は流体の流れやすさを表わします。
粘度が高いときインクは流れにくいので、インクフローは少ないです。
しかし、用紙の表面において、ペリカン ブラックはペリカン ロイヤルブルーよりにじみが多いので、筆跡が太くなっています (図19a)。
粘度が高くなっても、インクフローの減少より、にじみの方が筆跡の太さに影響しています。用紙の裏面において、ペリカン ブラックはペリカン ロイヤルブルーより裏抜けが多いです (図19b)。
今度は、万年筆はフェリチータ (細字F) を使用して、モンテグラッパのブラックとモンテグラッパのブルーのインクフロー、にじみやすさ及び裏抜けを観察します。
ただし、粘度の大小によるインクフロー、にじみやすさ及び裏抜けの違いをはっきりさせるために、モンテグラッパのブラックは水分をできるだけ蒸発させて粘度を上げて煮詰まった状態のインク (粘度 (強)) を使用します。
用紙の表面において、モンテグラッパのブラック粘度 (強) の筆跡が細いことは、粘度が高いとき、
インクの流速は遅いので、インクフローが渋くなることを表しています。
モンテグラッパ ブルーの筆跡が太いことは、粘度が低いとき、インクの流速は速いので、インクフローが良くなることを表しています。
しかし、モンテグラッパのブラック粘度 (強) はモンテグラッパ ブルーよりにじみが多いです(図20a)。
用紙の裏面においては、モンテグラッパのブラック粘度 (強) はモンテグラッパ ブルーより裏抜けが多いです(図20b)。

図19a 粘度の高低によるにじみやすさの比較1 (表面)ペリカン ブラック (上)、ペリカン ロイヤルブルー (下) 万年筆:トレドM900 (極細EF)

図19b 粘度の高低による裏抜けの比較1 (裏面)ペリカン ブラック (上)、ペリカン ロイヤルブルー (下) 万年筆:トレドM900 (極細EF)

図20a 粘度の高低によるにじみやすさの比較2 (表面) モンテグラッパ ブラック 粘度 (強)(上)、モンテグラッパ ブルー (下) 万年筆:フェリチータ (細字F)

図20b 粘度の高低による裏抜けの比較2 (裏面) モンテグラッパ ブラック 粘度 (強)(上)、モンテグラッパ ブルー (下) 万年筆:フェリチータ (細字F)
従って、粘度が高いときインクは乾きづらくて、にじみやすく裏抜けしやすく、粘度が低いときインクは乾きやすくて、にじみにくく裏抜けしにくいことが示されました。
普段、煮詰まるまで水分を蒸発させたインクを使うことはほぼないです。
よって、通常の使用では、粘度が高いとき、インクフローの減少より、にじみ・裏抜けの増加する影響力が強いので、筆跡は太くなると考えてインクを使っていただきたいです。
粘度が高いとき、流速は遅いので、インクフローが渋くなり、粘度が低いとき、流速は速いので、インクフローが良くなることを確認できました。
また、8章でも説明しますが、ペン芯と表面張力や粘度の関係性は深いですので、「粘度とインクフローの関係」は覚えておくとよいでしょう。

この章のまとめ:
・粘度が高いとき、インクは乾きづらくて、にじみやすく裏抜けしやすい。
・粘度が低いとき、インクは乾きやすくて、にじみにくく裏抜けしにくい。
・粘度が高いとき、インクの流速は遅いので、インクフローが渋くなる。
・粘度が低いとき、インクの流速は速いので、インクフローが良くなる。
・通常の使用では、粘度が高いとき、インクフローの減少より、にじみ・裏抜けの増加する影響力が強いので、筆跡は太くなる。
8.表面張力とインクフローの関係
さて、次は、あまり馴染みがないかもしれない表面張力について説明します。
万年筆インクにおいては、粘度だけでなく表面張力も重要な点になります。
表面張力とは液体の分子同士がまとまって表面積をできるだけ小さくしようとする性質のことです。水滴が球状をしているのは表面張力によって縮まろうとするからですね。
シャボン玉の表面張力について考えてみましょう。
ストローの先にただの水をつけて吹いても膨らみません。
ストローの先に洗剤を入れた水をつけて吹くと膨らんでシャボン玉になります。
水だけでは表面張力が大きすぎて膜を作れませんが、洗剤に含まれている界面活性剤が水の表面張力を小さくするためシャボン玉を作ることができます (図B)。

図B シャボン玉のスケッチ
実は万年筆のインクにも界面活性剤が含まれていて、界面活性剤が少ないとき表面張力は大きくなり、界面活性剤が多いとき表面張力は小さくなります (表1)。

万年筆のインクには界面活性剤が含まれているので、水 (20℃) よりも表面張力が低くなっています。
一般的に、万年筆インクの表面張力が高いと、ペン芯の櫛 (くし) から櫛へ流れていく力が強い、ということになりますから「流れやすくなる」と言えます。
ここからはかなり専門的な話になりますので、難しすぎる~!という方は枠の下まで飛んでください。
表面張力と毛細管現象、そしてペン先スリットの関係性
液体の表面に細管を立てると、液体は管内を上昇または下降する現象を毛細管現象と呼びます4) (図21a)。

図21a 毛細管現象のスケッチ

図21b 毛細管現象のスケッチ 表面張力Tが大 (左)、表面張力Tが小 (右)

図21c 毛細管現象のスケッチ 円管の直径dが小 (左)、円管の直径dが大 (右)
円管の直径をd、液体の壁に対する接触角をθ(シータ)、液体の密度をρ(ロー)、重力加速度をg、液面の平均の高さをh、表面張力をTとすると、
h=(4T cosθ)÷(ρgd)
この式は表面張力Tが大きいとき液面の高さhは高くなり、表面張力Tが小さいとき液面の高さhは低くなることを表わしています (図21b)。
液面の高さhだけ上昇または下降したとき管内の液体の容積は、万年筆においてインクフローに相当します。
よって、上式は表面張力が大きいときインクフローは良くなり、表面張力が小さいときインクフローは渋くなることを表わしています。
上式は円管の直径dが小さいとき液面の高さhは高くなり、円管の直径dが大きいとき液面の高さhは低くなることを表わしています (図21c)。
万年筆において、円管の直径dはニブの切り割り (スリット) の間隔に相当します。
よって、スリットの間隔が狭いとき、毛細管現象の働きやすさにより、インクフローは良くなります。
スリットの間隔が広いとき、毛細管現象の働きにくさにより、インクフローは渋くなります。
ただし、ハート穴からペンポイントに向かってスリットの間隔が平行にならずに狭くなっていかないと、
毛細管現象の働きにより、インクをペンポイントまで送ることができません (図22)。


図22 スリットの間隔 万年筆:モンテグラッパ フェリチータ (細字F)
ペン先調整において、インクフローを良くするときは、
ハート穴からペンポイントに向かってスリットの間隔が狭くなるように、スリットの間隔を広げたりして調整します。
つまりは、毛細管現象により、表面張力が高ければインクフローは良くなり、低ければインクフローは渋くなるはず、ということですね。
それでは、表面張力の大きさがインクフローに及ぼす影響について検証していきます。
表面張力が大きいインク及び表面張力が小さいインクをそれぞれ万年筆に入れて用紙に文字を書いて、上の理論計算が実際に成り立つのか考察します。
なお、実際のインクフローでは、粘度と表面張力のバランスがありますから、粘度の影響を小さくするために、粘度が近くて表面張力が異なるインクでインクフローを比較します。
求める条件を満たすインクとして、モンテグラッパのブルーとペリカンのエーデルシュタイン トパーズ (ターコイズ・ブルー) を選びました (表1)。
表面張力に関してモンテグラッパのブルーは高く、ペリカンのエーデルシュタイン トパーズは低いです。
ちなみにエーデルシュタインはペリカンの高級ラインのインクで、ロイヤルブルーと比べるとボトルのデザインが洗練されています(図23)。

図23 ペリカンのインクボトルデザインの比較 ロイヤルブルー(左)、エーデルシュタイントパーズ(右)

図24a 表面張力によるにじみやすさの比較 (表面)モンテグラッパ ブルー (上)エーデルシュタイン トパーズ (下) 万年筆:エキストラ地中海ブルー (極細EF)

図24b 表面張力による裏抜けの比較 (裏面 )モンテグラッパ ブルー (上)エーデルシュタイン トパーズ (下) 万年筆:エキストラ地中海ブルー (極細EF)
万年筆はエキストラ (EF) を使用して、モンテグラッパのブルーとペリカンのエーデルシュタイン トパーズのインクフロー、にじみやすさ及び裏抜けを観察します(エキストラは図6、14を参照)。
にじみやすさ及び裏抜けを明確にするために、紙は吸水性の良いコピー用紙を使用します。
筆圧、筆記角度、筆記速度、用紙により、にじみやすさ及び裏抜けの程度は変わることをご了承願います。
用紙の表面において、モンテグラッパのブルーの筆跡が太くて、エーデルシュタイン トパーズの筆跡が細いことは、
表面張力が大きいときインクフローは良くて、表面張力が小さいときインクフローは渋くなることを表しています(図24a)。
モンテグラッパのブルーはエーデルシュタイン トパーズよりにじんでいます。
用紙の裏面において、モンテグラッパ ブルーの裏抜けは多いですが、エーデルシュタイン トパーズの裏抜けは少ないです(図24b)。
従って、モンテグラッパのブルーのように表面張力が大きいとき、毛細管現象の働きやすさにより、
インクフローは良くなって、にじみやすく裏抜けしやすいことが示されました。
一方、エーデルシュタイン トパーズのように表面張力が小さいときは、毛細管現象の働きにくさにより、
インクフローは渋くなって、にじみにくく裏抜けしにくいことが示されました。
にじみ及び裏抜けが多いときは、表面張力の高いインクから低いインクに替えたり、
吸水性の低い用紙を使うことにより、にじみ及び裏抜けを少なくすることができます (「5. インクと紙には相性がある!」参照)。
また、このあとの章でも説明しますが、ペン芯と表面張力や粘度の関係性は深いですので、「表面張力とインクフローの関係」は覚えておくとよいでしょう。

この章のまとめ:
・表面張力とは液体の分子同士がまとまって表面積をできるだけ小さくしようとする性質のこと。
・万年筆のインクには界面活性剤が含まれていて、界面活性剤が少ないとき表面張力は大きくなり、界面活性剤が多いとき表面張力は小さくなる。
・液体の表面に細管を立てると、液体は管内を上昇または下降する現象を毛細管現象と呼ぶ。
・ハート穴からペンポイントに向かってスリットの間隔が狭くなっていかないと、毛細管現象の働きにより、インクをペンポイントまで送ることができない。
・表面張力が大きいとき、毛細管現象の働きやすさにより、インクフローは良くなって、にじみやすく裏抜けしやすい。
・表面張力が小さいとき、毛細管現象の働きづらさにより、インクフローは渋くなって、にじみにくく裏抜けしにくい。
9.気液交換とインクフローの関係 -ペン芯の構造がインクフローに影響を及ぼす-
ここでは、ペン芯の構造(万年筆のインクが出てくる心臓部!)について説明してきます(図C)。
万年筆を使う上でとても重要な部分になりますので、この構造についてはぜひ知っておくとよいでしょう。
ペン先から用紙に流れたインクの体積と同じ量の空気を胴軸内部のインクタンクに吸い込むことを気液交換と呼びます4) (図25~27)。
インク溝は毛細管現象の働きにより、インクをタンク内から引き出して、ペン先まで導きます。(毛細管現象は「8. 1表面張力と毛細管現象、そして、ペン先スリットの関係性」参照)。
インク溝は胴軸からペン先に向かって間隔が狭くなっていかないと、毛細管現象がうまく働かず、インクをペン先まで送ることができません5) 。
ペン先のスリットの間隔よりも用紙の繊維の隙間の方が狭いので、毛細管現象によりペン先から用紙へインクが流れます。
よって、ペン芯には、インクが通るインク溝、空気を取り入れる空気溝、余分なインクを溜めておく櫛溝、櫛溝 (くしみぞ) の空気を逃がす空気逃げ溝があります。
醤油差しと同様に、空気溝が塞がってしまうとインクは出て来なくなります。
ここで、気液交換において、インクが減った分だけペン芯の空気溝から胴軸内部のインクタンクへ空気 (気泡) を吸い込む仕組みを説明します。

図C 万年筆 ペン先分解図
※万年筆を分解して壊してしまった場合、メーカー保証の対象外となるので、個人の判断で分解をしないでください。
では万年筆で線が書ける仕組みをおさらいしておきましょう!
ペン先から用紙に流れたインクの容積と同じ量の空気を胴軸内部のインクタンクに吸い込むことを「気液交換」と呼びます5) (図26、27)。

図25 気液交換のスケッチ

図26 気液交換のモデル

図27 櫛溝の間隔 インク:モンブラン ロイヤルブルー 万年筆:マイスターシュテュック シルバー・バーリー(F)
気液交換でインクが出てくる仕組み
気体の圧力を気圧と呼びます。大気の重量により地上にかかる圧力を大気圧と呼びます。
大気圧 (1気圧) は標準圧力とも呼ばれていて、1気圧=101325[Pa(パスカル)]です3)。
空間内の気圧が外部よりも低い状態を陰圧 (負圧) と呼びます。空間内の気圧が外部よりも高い状態を陽圧 (正圧) と呼びます。
また、容器の内側の圧力を内圧と呼びます。容器の外側から加わる圧力を外圧と呼びます。
もし、ペン先から用紙にインクが流れる際に、空気溝が詰まっていると、
インクタンク空気が入らないので、タンク内の空気の圧力は大気圧より低い陰圧になって、ペン先から用紙にインクが流れなくなります。
ペン先から用紙にインクが流れる際に、空気溝からタンクに空気 (気泡) を送るので、タンク内の空気の圧力が大気圧より高い陽圧になって、タンク内の空気がインクを押し出します5)。
タンクの容積は変わらないので、インクの無くなった部分が真空にならないように、ペン先から用紙に流れたインクの体積と同じ量の空気をタンクに吸い込みます (図25、26)。
飛行機に万年筆を持ち込むとインク漏れする理由
飛行機の中において、上空では気圧が低いので (例:0.8気圧)、インクタンク内の空気の圧力 (内圧) は機内の圧力 (外圧) より高くなって陽圧になります。
内圧と外圧の圧力差が大きいので、タンク内の空気がインクを強く押します。
たいていの場合は押し出されるインクが少ないことにより櫛溝で溜められますが、押されるインクの量が多いとインク漏れを起こします。
従って、高度差などの影響により外圧が下がった場合、タンク内の空気により押されるインクの量が櫛溝で溜められる量を超えるとインク漏れを起こします5)。
飛行機に乗る際はタンク内を空にするか、タンク内の空気をできる限り少なくするためにタンク内をインクで満たすと、上空でインク漏れを起こしません。
筆記しないときの万年筆の保管
地上においても飛行機の中でも、万年筆を下に向けて保管すると重力の影響によりペン先からインクが出てくることがあるので、
筆記しないときはペン先が上向きになるように万年筆を保管します。
ピストン吸入式のインク吸入の仕組み
今度は、ピストン吸入式において、インクボトルからのインク吸入を考えます。
尻軸を左 (反時計回り) に回転させて、ピストンを下げると、インクタンクは陽圧 (正圧) になるので、タンク内部の空気をボトルに吐き出します。
ピストンが下がりきった所で、タンク内部の圧力は均衡状態、即ちゼロになります。
尻軸を右 (時計回り) に回転させて、ピストンを引き上げると、タンク内部は陰圧 (負圧) になるので、ボトルからインクを吸い上げます (図28a)。
コンバーター式も同様です (図28b)。
従って、ピストン吸入式およびコンバーター式のインク吸入は、ピストンを下げるとタンクは陽圧になり空気を吐き出して、ピストンを上げるとタンクは陰圧になりインクを吸い上げます。

図28a ピストン吸入式におけるインクの吸入

図28b コンバーター式におけるインクの吸入
ペン芯の空気溝とインクフローの関係
ペン芯の空気溝とインクフローの関係を考えます。
インクフローを良くするには、たくさんの空気をインクタンクに送る必要があるので、空気溝を大きくします。
インクフローを渋くするには、インクタンクに送る空気を減らす必要があるので、空気溝を小さくします5)。
よって、空気溝の大きさはインクフローを決める重要な要素になっています。
従って、同じモデルでもペン芯は字幅ごとにインクフローの差があります。
例えば、ペリカンのスーベレーンM800の細字 (F)、中字 (M)、太字 (B) におけるペン芯はそれぞれ異なるペン芯を使用しています。
櫛溝の間隔は一定ではありません6) (図25,27)。
首軸付近において、櫛溝の間隔は狭く毛細管現象が働きやすいので、余分なインクは櫛溝に吸い寄せられますが、
ペン先付近において、櫛溝の間隔は広く毛細管現象が働きにくいので、水圧が一定の高さ以上にならないと、インクは櫛溝に吸い寄せられません。
首軸からペン先に向かうほど水圧は高くなるので、櫛溝の間隔を調整することにより、
ペン芯からペン先へ供給されるインクの量を一定に保ち、インクのボタ落ちを防いでいます5)。
インクフローを決める要因
インクフローはインクの粘度、表面張力、気液交換などの条件により決まります (「7. 粘度とインクフローの関係」「8. 表面張力とインクフローの関係」参照)。
毛細管現象、用紙によるインクの吸水、気液交換の3つがそろって、インクは途切れることなく用紙に出てきます (用紙によるインクの吸水は「5. インクと紙には相性がある!」参照)。
粘度が高いとき、粘度が低いとき、途切れることなくインクが出るインクフローのことをそれぞれぬらぬら、サラサラと表現します。
いろいろな条件のバランスがあるために、例えばイタリアのペンに国産のインクを入れたらボタ落ちしてしまった…とか、
あるいはパーカーに○○のインクを入れたらインクが出てこない!ということなんかが起こるわけです。

この章のまとめ:
- ペン先から用紙に流れたインクの体積と同じ量の空気をタンクに吸い込むことを気液交換と呼ぶ。
- インク溝は毛細管現象の働きにより、インクをタンク内から引き出して、ペン先まで導く。
- インク溝は胴軸からペン先に向かって間隔が狭くなっていかないと、毛細管現象の働きにより、インクをペン先まで送ることができない。
- ペン先のスリットの間隔よりも用紙の繊維の隙間の方が狭いので、毛細管現象によりペン先から用紙へインクが流れる。
- 高度差などの影響により外圧が下がった場合、タンク内の空気により押されるインクの量が櫛溝で溜められる量を超えるとインク漏れを起こす。
- ピストン吸入式およびコンバーター式のインク吸入は、ピストンを下げるとタンクは陽圧になり空気を吐き出して、ピストンを上げるとタンクは陰圧になりインクを吸い上げる。
- インクフローを良くするには、たくさんの空気をインクタンクに送る必要があるので、空気溝を大きくする。
- インクフローを渋くするには、インクタンクに送る空気を減らす必要があるので、空気溝を小さくする。
- 首軸からペン先に向かうほど水圧は高くなるので、櫛溝の間隔を調整することにより、ペン芯からペン先へ供給されるインクの量を一定に保ち、インクのボタ落ちを防いでいる。
- インクの粘度、表面張力、気液交換などの条件により、インクフローが決まる。
- 毛細管現象、用紙による吸水、気液交換の3つがそろって、インクは途切れることなく用紙に出てくる。
- 粘度が高いとき、粘度が低いとき、途切れることなくインクが出るインクフローのことをそれぞれぬらぬら、サラサラと表現する。
10.万年筆の棚吊りについて
インクタンクの中のインクの量が少なくなると、インクが壁面に貼り付いてしまい、ペン先の方に流れて来なくなる状態を棚吊り (たなつり) と呼びます (図29)。
コンバーター式や透明な軸だとわかりやすいですが、どのユーザーでも起こる可能性がある現象です。

図29 棚吊り インク:ペリカン ブラック 万年筆:フェリチータ(細字F)
なぜ棚吊りが起こるのでしょうか?分子同士が引き合う力を分子間力と呼びます。インクの分子間力は網のようなバリアーを形成して、他の分子が入ってくることを防いでいます。分子間力が強いとき、網の目が細かくなり、バリアーは強くなります。
分子間力が弱いとき、網の目が粗くなり、バリアーは弱くなります (図30)。

図30 分子間力とバリアー
表面張力が強いとき、タンクの中の空気はインクの分子間力のバリアーを破ることはできず、インクは落ちて来なくなります5)。
つまり、気液交換が行なわれず、インクが流れなくなります (気液交換は「9.気液交換とインクフローの関係」参照)。
カートリッジの中には、内部の表面がギザギザになっていたり、少し突起した縦筋が入っているものもありますが、
このような工夫をすることで表面張力は働きにくくなります。パイロットのコンバーター「CON-40」にはインク小さな金属球が4個入っています。
この金属球が動くことにより、インクを撹拌して、インクの表面張力を下げて、分子間力のバリアーを壊して、
気液交換が行なわれるようになり、インクがスムーズに流れるようになります5)。
パイロットのコンバーター「CON-70N」に入っている金属パイプも金属球と同様の働きをします (図31)。

図31 PILOTのコンバーター 上:CON-40,下:CON-70N
棚吊りが発生したら、コンバーターを軽く叩いてインクを落としたり、あるいは万年筆を軽く振って金属球を動かして、
コンバーターの壁面に貼り付いたインクを下部に落とすことにより、再びインクが流れるようになります。
もし、このような操作を行なってもインクが流れなかったら、インクを入れ直して、コンバーターの中をインクで満たします。

この章のまとめ:
- インクタンクの中のインクの量が少なくなると、インクが壁面に貼り付いてしまい、ペン先の方に流れて来なくなる状態を棚吊りと呼ぶ。
- 棚吊りが発生したら、コンバーターを軽く叩いてインクを落としたり、あるいは万年筆を軽く振って金属球を動かして、コンバーターの壁面に貼り付いたインクを下部に落とすことにより、インクが流れるようになる。
11.万年筆インクの水素イオン指数pH (酸性・中性・アルカリ性)
万年筆インクの特徴を表すときに、「酸性・アルカリ性」というのを聞いたことはありますか?
水素イオン指数pH (ペーハーまたはピーエッチ) は、液体の酸性・アルカリ性 (塩基性) の程度を表わす指数です。

ここからpHについて説明しますが、難しい!という方は枠の下まで飛んでください。
6.02×1023 個の粒子の集団を物質量と呼び、1mol (モル) と表わします。
モル濃度は溶液1L (リットル) あたり溶質が何mol溶けているかを表わして、単位はmol/Lです。
水素イオンH+のモル濃度を水素イオン濃度と呼び、[H+ ]と表わします。
水酸化物イオンOH-のモル濃度を水酸化物イオン濃度と呼び、[OH-]と表わします6)。
[H+]と[OH-]の単位は共にmol/Lです。水素イオン濃度[H+]と水酸化物イオン濃度[OH-]の積は一定です。 [H+] [OH-] =1.0×10-14水素イオン指数pHと水素イオン濃度[H+ ]の関係は、常用対数log (ログ) を用いると
pH=-log10 [H+]
万年筆インクはインクごとに組成が変わるため、pHが異なります。
pHの範囲は0から14です (図32)。[H+]が高くて、[OH-]が低いとき、pHは小さくなり、酸性になります。
[H+]と[OH-]がほぼ等しいとき、pHは7前後になり、中性になります。 [H+]が低くて、[OH-]が高いとき、pHは大きくなり、アルカリ性になります。
図32 水素イオン指数pHと水素イオン濃度[H+]の関係のグラフ
水素イオン指数pHは、酸性では7より小さく、中性では7前後、アルカリ性では7より大きいです (図33)。
青色のリトマス紙が赤色に変わるとき酸性です。青色・赤色のリトマス紙ともに色が変わらないとき中性です。
赤色のリトマス紙が青色に変わるときアルカリ性です。
pHの目安は、0以上3未満だと強酸性、3以上6未満だと弱酸性、8以上11未満だと弱アルカリ性、11以上だと強アルカリ性です (図33)。

図33 水素イオン指数pH (酸性・中性・アルカリ性) (強酸性、弱酸性、弱アルカリ性、強アルカリ性)
例えば、プラチナ万年筆の場合、インクの大半が中性から弱アルカリ性 (pHは7前後から11)、ブルーブラックとクラシックインクはpH2前後の強酸性です1) (表1参照)。ペリカンのロイヤルブルーは強酸性、エーデルシュタイントパーズは弱酸性です (表1参照)。

古典インクは酸性でインクに天然の成分をしようしているため微細な沈殿を生じることがありますが、筆記に影響はありません。
酸性のインクはステンレスや金ペンのペン先や首軸のリングを腐食させてしまうことがあるので、インク吸入後はペン先と首軸をきれいに拭いておきましょう。
一方、アルカリ性のインクはアルカリ域で使える防カビ剤が限られているので、防腐対策が難しいです1)。
酸性のインクを使用した後に万年筆を洗浄せずにアルカリ性のインクを使用すると、生成された塩 (えん) がぬめりとして現れて、インクの流れが止まってしまうので注意が必要です。
ただし、プラチナ万年筆の染料インクであるミクサブルインクは、表面張力・粘度・pH値を揃えているので混合可能です。ちなみに、セーラー万年筆のストーリアは混合可能な顔料インクです。

この章のまとめ:
- 水素イオン指数pHは、液体の酸性・アルカリ性 (塩基性) の程度を表わす指数である。
- 水素イオン指数pHは、酸性では7より小さく、中性では7前後、アルカリ性では7より大きい。
- pHの目安は、0以上3未満だと強酸性、3以上6未満だと弱酸性、8以上11未満だと弱アルカリ性、11以上だと強アルカリ性である。
- プラチナ万年筆の場合、インクの大半が中性から弱アルカリ性 (pHは7前後から11)、ブルーブラックとクラシックインクはpH2前後の強酸性である。
12.万年筆インクの濃淡
万年筆のインクの醍醐味ともいえる、色の濃淡。これはいったいどうして起こるのでしょうか?
万年筆インクで書いた用紙の筆跡において、濃い部分と薄い部分が現れることを濃淡と呼びます。
筆跡が微小な点のとき、濃淡は出ません。筆跡が線のとき、始点と終点があるので、インクが溜まる部分とそうでない部分で濃淡が出ます。
気液交換によりペン先まで導かれたインクは、ペン先のスリットの間隔よりも用紙の繊維の隙間の方が狭いので、毛細管現象によりペン先から用紙へインクが流れます。(「9. 気液交換とインクフローの関係」参照)。
よって、用紙の平面上でインクがどのように動くかによって濃淡の出方が変わります。
プラチナ万年筆の銀無垢鍛金磨き鍛金磨き (太字B) に純正の染料インクであるブラック、レッド、および古典インクのブルーブラックを入れて濃淡を確認すると、濃淡はブルーブラック>レッド>ブラックの順にはっきりしています (図34)。

図34 染料インク、古典インクの濃淡インク:黒(左)、赤(中)、ブルーブラック(右) 万年筆:プラチナ万年筆 銀無垢鍛金磨き (太字B)
染料インクは、用紙の中まで入り込むので、濃淡が出やすいです。古典インクも、染料インクの成分を含んでいるので、濃淡が出やすいです。
顔料インクは固まると内部部品を交換したり、ペン芯の櫛溝で固まるとペン芯を交換することになります。スリップシール機構が搭載してインクが乾きにくいプラチナ万年筆のプロシオン (中字M) に、純正の顔料インクのカーボンブラック、顔料ブルーを入れて濃淡を確認すると、共に濃淡が出にくいです (図35)。
顔料インクは、用紙の表面に付着するので、濃淡が出にくいですが、筆跡がはっきりとしていて、にじみにくくて、裏抜けしにくいです。
用紙上の顔料インクは乾くと水に強いので、大切なスケジュールを記録する手帳などで活躍します。
染料インクは、用紙の中まで入り込むので、濃淡が出やすいです。
古典インクも、染料インクの成分を含んでいるので、濃淡が出やすいです。
顔料インクは固まると内部部品を交換したり、ペン芯の櫛溝で固まるとペン芯を交換することになります。スリップシール機構が搭載してインクが乾きにくいプラチナ万年筆のプロシオン (中字M) に、純正の顔料インクのカーボンブラック、顔料ブルーを入れて濃淡を確認すると、共に濃淡が出にくいです (図35)。

図35 顔料インクの濃淡 インク:カーボンブラック(左)、顔料ブルー(右)万年筆:プラチナ万年筆 プロシオン (中字M)
顔料インクは、用紙の表面に付着するので、濃淡が出にくいのですが、筆跡がはっきりとしていて、にじみにくくて、裏抜けしにくいです。用紙上の顔料インクは乾くと水に強いので、大切なスケジュールを記録する手帳などで活躍できます。
今度はペリカンのトレドM900 (極細EF) とスーベレーンM800 (中字M) でインクの濃淡を比較します (図36)。字幅が太くなるとインクフローが多いので、筆跡に濃淡が出やすいです。字幅が細くなるとインクフローが少ないので、筆跡に濃淡が出にくいです。
ただし、用紙ごとにインクの吸収性は異なるので、用紙によって筆跡の濃淡は変わります (「5. 用紙とインクの相性」参照)。

図36 字幅による濃淡の比較 インク:ペリカン ロイヤルブルー 万年筆:トレドM900 極細EF (上)、スーベレーンM800 中字M (下)用紙:マルマン ニーモシネ

この章のまとめ:
- 万年筆インクで書いた用紙の筆跡において、濃い部分と薄い部分が現れることを濃淡と呼ぶ。
- 染料インクは、用紙の中まで入り込むので、濃淡が出やすい。
- 顔料インクは、用紙の表面に付着するので、濃淡が出にくい。
- 古典インクは、染料インクの成分を含んでいるので、濃淡が出やすい。
- 字幅が太くなるとインクフローが多いので、筆跡に濃淡が出やすい。
- 字幅が細くなるとインクフローが少ないので、筆跡に濃淡が出にくい。
- 用紙ごとにインクの吸収性は異なるので、用紙によって筆跡の濃淡は変わる。
13.パイロットインクのレビュー
このコラムでは、インクの種類、用紙と紙の相性、粘度、表面張力、毛細管現象、気液交換、棚吊り、pH、濃淡などの話をしてきました。
これらの要素を踏まえて、PILOTのインクの黒 (ブラック)、色彩雫の3色 (冬柿、紺碧、深緑) をレビューします (図37abc)。
万年筆はPILOTのカスタム URUSHI 茜朱 (中細FM) 、用紙はコピー用紙を使用します。
色彩雫は様々な色のバリエーションが存在して、それぞれ成分が異なるので、このレビューの結果がすべての色彩雫に適用されるわけではないことをご了承願います。
カスタム URUSHI 茜朱には大型の30号のニブが付いています。
このニブは柔らかくてしなりがあり、インクフローがなめらかなので、ふわふわな書き味を持っていることに魅力を感じます。
ただし、柔らかなニブに対して筆圧が強すぎると、切り割り (スリット) が開いてペンポイントの左右の高さに食い違いが起こり、インクフローが悪くなることがあるので、筆圧に注意です。
また、カスタム URUSHIのコンバーターはCON-70Nで、棚吊りは起こりにくいです。

図37a インク:パイロット ブラック、色彩雫 冬柿、紺碧、深縁万年筆:パイロット カスタム URUSHI 茜朱 (中細FM)

図37b PILOTインクのにじみやすさの比較 (表面)インク:パイロット 黒 (ブラック)、色彩雫 冬柿、紺碧、深縁万年筆:パイロット カスタム URUSHI 茜朱 (中細FM)

図37c PILOTインクの裏抜けの比較 (裏面)インク:パイロット 黒 (ブラック)、色彩雫 冬柿、紺碧、深縁万年筆:パイロット カスタム URUSHI 茜朱 (中細FM)
パイロットの高級ラインのインクである色彩雫はおしゃれなボトルデザインで、色の名前も和風で特徴があり、赤、青、緑という単純な色ではないことに色の深みを感じます。
冬柿は柿のオレンジ色が入った赤、紺碧は夏の青空、深緑は山の緑のような色彩です (図37abc)。
色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) の表面張力は低くて、インクフローが渋めなので、筆跡が細くて、にじみにくく裏抜けしにくいです。
黒 (ブラック) は筆跡がさらに細くて、にじみやすく裏抜けしやすいので、色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) より粘度が高いのではないかと考えています。
黒 (ブラック)、色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) は水素イオン指数pHより、弱アルカリ性です。
色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) は黒 (ブラック) と比べると、筆跡に濃淡が出ています。
なお、黒 (ブラック)、色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) の表面張力・粘度・pHは表1に記載しています。

この章のまとめ:
- ニブは柔らかくてしなりがあり、インクフローがなめらかな場合に、ふわふわな書き味になる。
- 色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) の表面張力は低くて、インクフローが渋めなので、にじみにくく裏抜けしにくい。
- パイロットの場合、インクの大半は弱アルカリ性である。
- 色彩雫 (冬柿、紺碧、深緑) は筆跡に濃淡が出やすい。
14.終わりに
さて、ちょっと専門的ではありますが、インクの基礎知識についての記事はいかがでしたでしょうか?
難しい部分もあったかもしれませんが、こういった知識をある程度頭に入れておくと、
インクトラブルが発生したときに的確に対処できるかと思いますし、
万年筆を大切に長く使っていく上で大事なTipsになりますので、ぜひ知っておいていただければと思います。
1883年にルイス・エドソン・ウォーターマンが毛細管現象を応用して万年筆を創り出して、
その後様々なメーカーで設計者や職人さんが試行錯誤を繰り返して、デザインや機能性の優れた万年筆を製作したことにより、
万年筆はお客様にとって魅力的な製品になっているのだと思います。
万年筆、インク、用紙の三者の組み合わせにより万年筆の世界は広がります。
例えば、インクをブラックからブルーに変えて、用紙をMDノートからニーモシネに変えると、
異なる万年筆の魅力を引き出せます (図9~16参照)。
機会があればモンテグラッパに限らず、様々なメーカーの色彩のインクを使ってみたいところです (図24ab、37abc、38ab)。

図38a モンテグラッパ インクボトル2020 -50ml

図38b モンテグラッパ インク サンプル
例えば、現在では書類を作成するのにWord、Excelなどパソコンが主流ですが、
万年筆に赤色のインクを入れて書類の添削をすると、万年筆の活躍の幅が広がります。
何色か色分けして、細字の万年筆で手帳に予定を書き込むことも楽しいです。
各メーカーの万年筆にそれぞれの純正のインクを入れて筆記すると、自社の万年筆に合うインクを熱心に研究している様子が伝わってきます。
メーカーは万年筆に自社のインクを入れることを推奨していますが、
様々なメーカーのインクを入れて、書き味やインクフローの変化を楽しむことも万年筆の魅力のひとつ!
ただし、純正のインクを使用しないで他のメーカーのインクを入れて万年筆が故障した場合、メーカーの保証を受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。
特に高額品および限定品の万年筆には、顔料インク、古典インクの使用を避けて、染料インクを入れるべきです (「3. インクの種類」「12.万年筆インクの濃淡」参照)。
どこのメーカーのインクを選択すればよいのか、何色のインクを選べばよいのか悩んだら、万年筆の知識が豊富な佐藤店長に相談して決めるといいですね。
15. 万年筆調整師より、インクについてミニコラム

Il Duomo提携の調整師さんが、インクについて追記をしてくれたので
ぜひこちらも併せて読んでみてくださいね!
幾つかユーザー視点では見えにくいため触れられていなかった部分がありましたので、少し書かせていただきます。
国産三社、特にパイロットがわかりやすいのですが、パイロットのブルーブラックやブルー系は染料インクであるにもかかわらず耐水性が高く、
またシャバシャバ系のインクとして知られています。
これはキャップレスという看板モデル用にインクの粘性を調整したと言われています。
また通常モデルでのペン芯の設計構造上の都合で、古典インクでの使用を切り捨てる方向性になっており、
染料インクでの耐水性を上げる必要性からきています。
このように、万年筆とインクを同時に一社で製造している場合、
自社の万年筆に合ったインクの設計、インクに合った万年筆の設計がされていたりします。
近年増えている顔料インクなども、万年筆メーカーが作っているものは、
自社製品での使用が前提となっているため自社の万年筆のペン芯の設計で対応できる粘性表面張力、インク中の顔料粒子のサイズ等の研究がなされたものになっています。
インクメーカーが出している顔料インクもありますが、顔料インクとしては優れた特性を持っていて万年筆で使用ができると謳っていても、
実際に自分が持っているメーカーの万年筆で使用テストをされたかはわかりません。自己責任で使用してみるべきでしょう。
また、これはプラチナ万年筆の社長さんの講演で言われていたことなのですが、
顔料インクたとえカートリッジだったとしてもインクの鮮度というものは色や書き味に影響するとのことです。
出来立てのインクは違うんですよ!と力説しておられました。
確かにボトル開けたてと、暫く経ってからでだと、書き味も違いますし、色味も微妙に違う感じがします。
保存環境に注意しても古典インクは、色合いが変化していきます。染料インクも保存次第で全然違ってきます。
勿体無いからと、あまりに劣化してしまったインクを使っていると、
インク中にカビが発生し、万年筆のペン芯にカビがはびこることすらあります。
鮮度が良いインクを使って、楽しい万年筆ライフを送りたいものです。
16.参考文献
1)趣味の文具箱編集部:INK 万年筆インクを楽しむ本 (エイムック4617)、株式会社 ヘリテージ (出版当時は枻出版社) (2020)、pp.6-7、pp.30-33、pp.36-39、pp.140-141
2)趣味の文具箱編集部:趣味の文具箱 vol.40、株式会社 ヘリテージ (出版当時は枻出版社) (2016)、pp.49
3)中山泰喜:改訂版 流体の力学、株式会社 養賢堂 (1998)、pp.13-14、pp.20-21
4)パイロットコーポレーション:かく、がスキ
5)伊東道風:万年筆バイブル、株式会社 講談社 (2019)、pp.52-58、pp.102-110
6)加賀屋愛:NHK高校講座 テレビ学習メモ 第27回 水素イオン濃度とpH

つくしさん、インクの解説をありがとうございました!
物理的な側面、化学的な側面からの解説は、知っているようで知らないことがたくさんあり、とても勉強になりました。
インクの知識を深めると、メーカーのインクとペン芯、ペン体製作の切磋琢磨を想像することができ、よりいっそうリスペクトできそうです。
インクの注意すべき点や特徴を知り、安全に長く万年筆を使っていきたいですね。
万年筆の使い方・選び方に困ったら
万年筆の使い方、ペン先の選び方などご相談に乗れますので、気になる方はぜひLINE@でお気軽にトークしてみてくださいね(*'▽')
使い方・選び方に困ったら 万年筆の使い方・選び方で困ることがあればLINE@からお気軽にご質問くださいね!
Il Duomoの店長があなたのお好みの色や予算などを聞いて、リストアップすることもできますよ。 LINE@で商品のお問い合わせを簡単に♪さらに、LINE@限定でお得なクーポンを配布中。友だち追加してね。
IDで検索↓
【@vfj5261w】
スマートフォン、タブレットの方はこちら↓